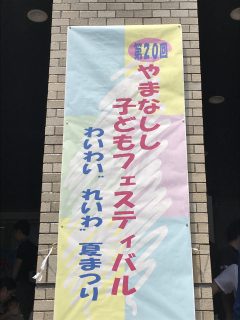井上先生による保育の表現技術(体育)の集中講義があり、小淵沢キャンパスの体育館に1年生が集合しました。
保育者になった場面を想定し、保育者役の学生が一人ずつ順番に子ども役の学生たちを相手に運動あそびを指導します。
学生はそれぞれ事前に指導案を書いてどんなあそびにするか考えていますが、うまくルールの説明ができるか実際にやってみることが大切です。模擬授業のでの失敗は貴重な経験になります。
ただ楽しいだけでなく、2人組みになっての押し相撲を導入とし、遊びを通じて子どもたちが全身を使う、仲間と協力することの大切さを学ぶ、といった「ねらい」に合わせた展開を考え、それが達成されたかをまとめとして評価していきます。
皆の前に出て大きな声で説明するには慣れも必要です。じゃんけんにさまざまな方法を取り入れた学生もいました。
全員がルールを理解し、集中して遊べているか目を配ります。場の雰囲気は、先生の声がけにより変化するそうです。
あそびのひとつには必ず何か教材を取り入れることになっており、新聞紙でボールを作って持ってきた学生もいました。
ボールを回し終わったら手をつないで寝転びましょう! どのチームが一番でしょうか?小さな子どもたちが飽きないようにする工夫が感じられます。
ボールをお腹に挟んで2人組で走る競争や、いつも行っているドッチボールのルールを変えた学生もいました。
野菜好きになってもらえるよう食育も考え、ピーマンやニンジンを描いた大きなカードをたくさん用意し、チームごとにカードめくりゲームを行いました。子どもたちが実際に行なっても盛り上がることでしょう!
最後に、この授業で保育者役を行なった学生たちが前に出て一言ずつ反省を述べました。もたついてしまったところや、説明の仕方を再考したいといった意見がありました。
さらに、井上先生からの講評や、学生同士がそれそれの運動あそびに対して感じた意見を書く時間もあり、全員で切磋琢磨しながら保育者としての力をつけるために励んでいます。